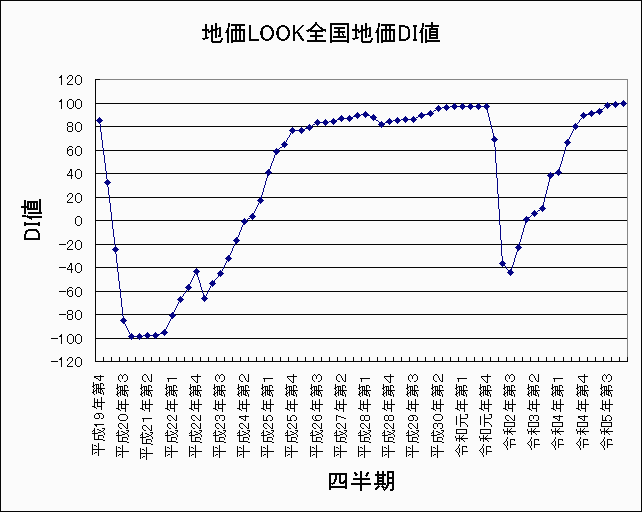である。
令和6年第1四半期の地価動向DI値(以下「地価DI値」と呼ぶ)は、
80-0
───── ×100 = 100
80
100である。
地価DI値の最高値は100である。
令和5年第4四半期の地価DI値は、99であった。令和6年第1四半期土地価格の地価DI値は、100である。
日本全国調査地点の土地価格は、上昇していると判断された。
調査全地点が上昇になるのは、初めての現象と国交省は云っている。
前期のDI値99の原因となったのは、東京の「青海・台場」が、全国で1地点「横ばい」であった為である。
今回は、その「青海・台場」も「上昇」に転じた。それによって、調査全地点の地価上昇という現象が実現した。
令和5年第4四半期の唯一地価「横ばい」として「青海・台場」の担当不動産鑑定士の地価動向コメントは、下記であった。このコメントは鑑定コラム2706)で記述した。下記である。
「当地区は大型商業施設が集積し、国内外から多数の観光客が訪れる観光スポットであるとともに、都心のサブマーケットとしてオフィスも集積するエリアである。
近年、当地区及び周辺においては、東京国際クルーズターミナルや都心部と臨海部を結ぶ環状2号線の整備、選手村の建設といった東京五輪開催のために様々な開発が行われた。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、来街者数は減少したが、渡航制限や感染症法上の位置付けの見直し等を受け、来街者数は持ち直し基調にある。 当地区内の大型商業施設では、飲食フロア、物販フロアともに当期も空き区画が散見されるものの、飲食店舗の売上高やホテルの稼働率は回復基調にある。
また、青海ST区画における開発計画の公表等、当地区の活性化への期待感が見られることから、取引需要は底堅く推移している。これらの状況を反映して、オフィス賃料、店舗賃料いずれも概ね横ばい傾向が続いており、取引利回りも横ばい傾向が続いたことから、当地区の地価動向は横ばいで推移した。
今後については、大規模開発計画への期待感とともに開発素地に係る取引需要は安定的に推移し、引き続き来街者数の持ち直し等による賑わいの回復が予想されるが、当面は当期の賃貸市場等の市況が続くと見込まれることから、将来の地価動向は横ばいで推移すると予想される。」(令和5年第4四半期 不動産鑑定士コメント)
令和6年第1四半期では横ばいから上昇に転じた。コメントがどの様に変化したか見ると、主な個所は下記である。
青海ST区画の構文の中では、「・・・取引需要は改善傾向にある。また、商業施設を中心に稼働率が上昇傾向にあり、近接する駅の乗降客も増加傾向にある。取引利回りは横ばい傾向が続いているものの、これらの状況を反映して店舗賃料が上昇に転じたことから、当地区の地価動向はやや上昇で推移した。」
と記す。
店舗客席の稼働率の上昇、駅乗降客の増加、店舗賃料の上昇によって地価が上昇していると判断している。
今後についての構文の中では、「・・・賑わいの回復が予想されることにより、商業施設を中心に当面は賃貸需要の強まりが続くと見込まれることから、将来の地価動向はやや上昇で推移すると予想される。」と記す。
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001748456.pdf)
過去1年少しの四半期の地価DI値を記すと下記である。
令和4年第3四半期 80
令和4年第4四半期 89
令和5年第1四半期 91
令和5年第2四半期 93
令和5年第3四半期 98
令和5年第4四半期 99
令和6年第1四半期 100
平成19年(2007年)第4四半期~令和6年(2024年)第1四半期までの地価DI値をグラフにすれば、下記グラフである。